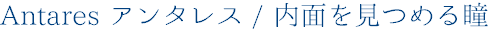
真夜中に目が覚めた。背中にじっとりと嫌な汗をかいていて、額に前髪がぺたりとくっついていた。先程まで見ていた悪夢が脳裏を過り、無意識にびくりと肩が震える。その振動で起こしたのか、隣から聞こえていたギルの寝息が止まった。首の下に差し込まれていた腕が曲げられ、半ば強制的に私を抱きしめると、寝起きの掠れた声で「どうした?」とギルが言った。もぞもぞと布団の中で寝返りを打って、体ごと私の方を向く。眠そうに何度か瞬いた後、ギルの瞳が私をまっすぐに捉えた。
「眠れないのか?」
もう片方の手で私の髪を撫でる。少し骨ばった大きな手から、温かい体温が伝わってきて、私はようやく安心して大きく息を吐いた。ギルが私の前髪を払って、額に口づけを落とす。
「ちょっと嫌な夢見て」
口に出すとあまりにも子供っぽい理由で、私は思わず照れ隠しの代わりに、上目遣いに口角だけ上げて、ふっと小さく笑ってみせた。そうしたらギルの瞳が呆れたように細められた気がして、ますますばつが悪い。
「なんだ、俺がいなくなる夢でも見たか?」
暗闇のなかでも、ギルがにやにやと嫌な笑みを浮かべているのが分かった。ぐっと息を詰まらせると、「図星かよ」と弾んだ声の後に、けせせ、と彼のいつもの笑い声が続いた。反抗のつもりで、唇を尖らせて彼を睨みつけたのに、ギルは別の意味にとったのか、もしくはただ自分のしたいようにしたのか分からなかったけれど、私の顎を掴んで上に向かせると、突き出した唇にそのまま自分の唇を重ねた。
何度か啄むように軽く触れあってから、彼の舌が私の唇をこじ開けた。優しく穏やかなのに、それでいて性欲のにおいのするキスだった。ギルの舌が私のそれを追いかけて、掴んで離さない。絡み合うたびに背筋をぞくりと何かが走って行って、それは先ほど恐怖に震えたものとは確かに違うのに、少し怖い。彼のシャツを掴んで、ぎゅっと目を瞑ると、瞼から快感による生理的な雫が零れた。それに気づいたギルが唇を頬に移動させて、それを舐めとる。
浅い呼吸を繰り返しながら彼を見ると、柔らかな視線が向けられる。彼のシャツに強く絡んだ私の指をひとつひとつ撫でながら解放させると、ギルはその手を自分のシャツのなかへ滑らせた。胸の、心臓のあたりまで持っていって、もう一度私の瞳を見つめると、にっと笑う。
「お前が嫌って言っても、ずっとそばにいてやるよ」
自信たっぷりなギルのその言葉は、道しるべのように暗闇のなかでもつやつやと光って見えた。手のひらから伝わる彼の鼓動が、じわりと私の内面を伝った。彼の手があやすように私の背中を撫で始める。今度は私が幸福な眠りに落ちるまで。
(2016.02.28)