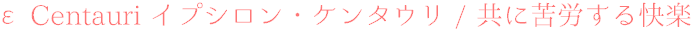
「大人になりたくない」
呟くと、隣でビール缶を傾けていた榛名がげほげほと派手に咽だした。気管にビールが入ったらしく、涙目で口元を押さえながらせき込む榛名の背中を幾度か擦った。なのに、榛名は御礼の言葉の代わりにじとりとした恩知らずな視線を飛ばしてくる。
「お前、二十歳も超えてんのに、なに言ってんだよ」
まだ少し気管にビールが残っているのか、どこかくぐもった榛名の声は、いかにもな呆れが含まれていて、私の中に初恋のような甘酸っぱい恥じらいがほんのり浮かんできた。それに気づかれまいと、取り繕うように唇の端を歪めた。
でも、だって、大人になりたくないのだ。二十歳を過ぎて、お酒は週末ごとに集まってどちらかの家で合法的に窘めるようになったけれど、中身は彼と出会った高校生の頃からまるで変わっていない気がした。あの頃の私の瞳には、大学生というものはもっと立派な大人に見えたのに、実際に大学生の今の私は、あの頃と変わらず幼くて、考えなしで、我儘だ。もうすぐ恐れていた就活シーズンがやってきて、うまくいけば働く大人だし、うまくいかなければ――どうなるのだろう。逃げ場などどこにもないのは分かっているのに、油断するとさっきみたいに泣き言が口をついて出る。こういうところ。こういうところも拙い。ああ、嫌だ嫌だ。
「榛名は大人になったねえ」
「何だそれ、ばばくせぇ言い方」
榛名が愉快そうに目を細める。むっとしたけれど、辛うじて顔には出さなかった。榛名の飲みかけのビールを奪い、一気に煽る。ぐびりぐびりと喉を豪快に鳴らしながら、ほろ苦い液体が体中を巡るのを感じていた。隣から小さなため息が聞こえてきたが、おかまいなしだ。何度目かの喉の音のあとに、空になったビール缶を片手でぐしゃりと潰した。榛名が声を立てて笑う。
「荒れてんなぁ」
「大人な榛名には私みたいな子供の気持ちは分かんないよ」
思ったより拗ねたような響きを持った言葉が、眼前に散らばって、ばつが悪くて目を伏せた。すると、榛名が私の頭に手を乗せ、わしわしと髪の毛を乱暴にかき混ぜた。「よーしよーし」と含み笑いの言葉が続いて、羞恥に瞼が焼ける。
「俺は早く大人になりたいわ」
「・・・何で?」
榛名は偉そうに私の頭に手を乗せたままだったけれど、それが不思議と嫌ではなくて、私は払いのけることもせずそれを享受したまま彼に尋ねた。待ってましたとばかりに頬を綻ばせた彼の瞳が不敵な光を帯びる。
「みたいな危なっかしいのの相手は、大人じゃねえと務まんねぇだろ」
にやりと口角を歪めると、また楽しそうに榛名が私の髪を弄ぶ。乱れた前髪で視界が遮られて、隙間から見える彼の顔が昔と同じように無邪気に見えて安心した。「ま、骨は拾ってやっから」という言葉が続いて、私も対抗するようにその言葉を繰り返した。
「じゃあ、榛名の骨は私が拾ってやるわ」
「お、言うじゃん」
にっと歯を零した幼い笑みが重なった。
(2016.02.29)