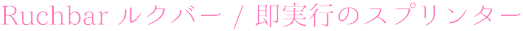
「なあ、って結構目悪いの?」
田島くんが私の前の席の椅子の背もたれを両手で抱えるようにして、行儀悪く跨って座った。がやがやと洪水みたいにざわめく昼休みの教室に、田島くんが私を訪ねて来るなんて意外だった。確かに少し前から彼とは所謂彼氏彼女の関係になったのだけど、田島くんは相変わらず野球に打ち込んでいて、私はそれを放課後のオレンジ色のフェンス越しに眺めて、ごくまれに目が合う瞬間を楽しみにしているだけだ。そりゃあたまに一緒に帰ったり、出かけたりはするけど、二人の間に色っぽい空気が流れることはなくて、私だけがどきどきそわそわしていて、片思いのときとあまり変わらないなあと、肩を竦めながらも安心していた。
だから、彼がわざわざ昼休みに私のところに来てくれるなんて、驚き以外の何物でもなくて、私が田島くんの質問を理解するまでいつもより時間がかかったのは、仕方のないことなのだ。
「聞いてんのかー?」
田島くんが軽く首を傾げながら、私の目の前でひらひらと手を振る。私の机の上に肘をついて、もう一度さっきの質問を繰り返した。彼の顔が急に近づいて、狼狽して飛びのくように距離をとると、田島くんがむっとしたように眉を顰めた。私は取り繕うように思わずのけぞった姿勢を正して、椅子に座りなおす。
「結構、悪いかなあ。たぶん0.1もないくらい」
「へえ。なあ、ちょっと視力検査させてよ」
いたずらっこみたいに、にっと笑って、田島くんが私の眼鏡に手を伸ばした。反射的に逃げるように身を捩ろうとしたけれど、彼のスピードには到底敵わず、私の視界は一気にぼやけてしまう。田島くんが眼鏡を折り畳んで、後ろ手に自分が借りている椅子とペアになっている机に置いた。咄嗟に取り返そうとした私の動きに気づかれてしまったみたいだ。「なんか書くもん貸して」と至極楽しそうな彼の声が聞こえてくるから、私も観念してこの「遊び」に付き合うことにした。
「これは?」
「んー・・・ちょっと見えない」
ノートを少しずつ近づけながら、確かめるように田島くんが問いかける。けれど、思いのほか小さく書かれてしまった字は、靄にかかったみたいにぼやけたままで、一向に判然としない。天真爛漫な田島くんの案外といじわるな面が垣間見えて、呆れと一緒に知らず知らずに頬が緩んだ。田島くんは折り曲げたノートの向こうで見えなくて、このだらしない顔が見られなくてよかったと思った。
「じゃあ、これは?」
顔面すれすれまで一気に近づいてきたノートに、私は思わず噴き出して、「近すぎて見えないよ」と笑い交じり言った。すると、すぐにさっとノートが顔の横に避けられたかと思うと、その向こうから突然田島くんの顔が目前に現れて、彼の前髪が私の額をくすぐった。それからすぐに唇になにかが触れたのが分かった。どきりと心臓が跳ねて、目を白黒させる。眼前の田島くんはさっきと同じように悪ガキみたいに口の端でカーブを描くと、「ちゅーしてやったぜー」と私にだけ聞こえるくらいの大きさで言った。薄いノート一枚で隔離された二人だけの空間は、ゆっくり時間が流れていて、瞬きもうまくできない。
(2016.02.28)