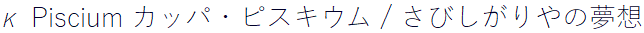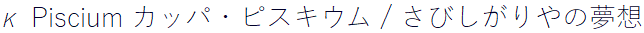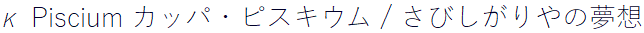
「人の家の明かりってなんだか温かく感じないかい?」
夕飯の材料の買い出しに二人でスーパーへ向かっているときだった。アルは真っ赤なスニーカーを履いていて、私の右手をしっかり握りながらそうたずねた。
私とアルの歩幅は随分と違っていたが、私はひとりのときよりすこしだけ早く、アルはすこしだけゆっくり歩きながら、二人同じペースで歩いていた。こういうとき、いいなあと思う。最初の内はお互いペースを合わせるのが下手で、私はアルに気を遣わせまいと大股かつ猛スピードで歩いていた。それはさながらど素人のど下手な競歩のようで、ひどく滑稽に見えていただろう。
「明かりかぁ…」
私は独り言のつもりでちいさく呟いた。
灰色の地面が濃く黒く、夕闇に染め上げられていく。それに合わせるようにぽつりぽつりと街灯がともり、私たちの歩く道沿いに建つ家々の窓から光が漏れ出していた。
「どうしてか分からないけど、時々ぎゅっとこのあたりが締めつけられる感じがするんだ」
アルが空いている方の手で胸のあたりを押さえた。ぎゅっと指が丸められて、Tシャツがくしゃりと皺になるのが見えた。その姿は、まだ何かを言い足りていないような感じがして、私は黙ってアルを見ていた。
まっすぐ伸びる夜道の先を見つめていたアルの顔が車道の方へ向けられる。黙らないでくれよ。アルが言った。それは不服そうな、けれども本当のところはただ単に照れているような言い方だった。こういうところは本当に兄弟でそっくりだ。それを言葉にすると、本格的に拗ねられそうなので、口には出さないけれど。
人の家の明かりは確かに温かい感じがする。小説や映画のなかでもよく、孤独なひとが家の明かりを眺めながら切なさに浸る場面はよく見る。けれども多分、私にとっては、隣の彼を見ているときの方が、もっともっと明るくて温かくて胸をぎゅっとしめつけられる感じがしている。
そう考えて、自分で自分が恥ずかしくなってしまった。体温の上がった頬から熱を吐き出すように、ふふっと息を漏らした。
「笑うのはよくないんだぞ」
アルが言った。今度は不機嫌そうな言い方だった。
「違う違う。私が、アルよりも恥ずかしいこと考えたから笑えたの」
車道側を向いていたアルの顔が、こちらに戻ってきた。
「君、暗に俺が恥ずかしいこと言ったって言ってないかい?」
「え。んー…ごめん?」
謝る気は全然なかったから、言いながら小首を傾げてしまった。私を見つめるアルの目が皮肉っぽく細められたが、そこに嫌な気持ちは含まれていない。戯れと愛情がまざったかたちをしていている、と思った。
「人の家の明かりって確かに温かい感じがする。そこに人がいて、生活の呼吸音が聞こえる感じがするからかなぁ」
アルの目がいつものきれいなかたちに戻ったのを確認してから、私は言葉を続けた。
「けどね、私はアルを見ているときの方が、もっと温かい気持ちになるよ。切ない気もするし、時々泣きそうにもなるけど、すごく明るくて温かい感じ。今も、そう」
今度はアルが黙ってしまった。私は恥ずかしさと熱を吐き出すように、へへへと笑って見せる。熱い吐息が漏れた気がした。
「の方が全然恥ずかしいこと言ってるんだぞ!」
しばらく考え込んでからそう言ったアルも、私と同じくらい赤い顔をしているように見えた。道路はもう夜に塗りつぶされていて、等間隔に立っている街灯の光はスポットライトみたいに私たちを照らしていた。あ、また恥ずかしいこと考えている。そう思ったが、なんだか今日はもう恥ずかしいことばかりを言ってしまおうという気にもなっていた。
だって今、私はきっととても幸福なのだ。
(2016.06.07)
Close