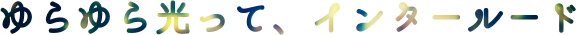
西に回った太陽のまぶしい光をじっと眺めながら歩いていると、アスファルトに跳ね返された陽射しがかすかにゆらめいて見えた。不思議と風はなく、ただひたすらに夏の残り香のする熱が散乱しているような午後だった。わたしは一度だけぎゅっと瞼を閉じ、昨日の御手杵の弱り切ったように下がったまゆげを思い出した。昨夜から携帯の電源は切ったままにしていた。彼と一緒に住むようになってから、こんなにも彼を遠くに感じたのは初めてだった。
昨夜、わたしたちはソファに並んで座り、キンキンに冷やしたビールを飲んでいた。テーブルの上には帰宅後15分ほどでささっと彼が作ってくれた簡単なおつまみが並んでいた。そのときわたしは妙に陽気になっていて、戯れに野菜スティックを口にくわえ、ん、と御手杵に向けた。ポッキーゲームならぬ野菜スティックゲーム。御手杵はくくっと喉のおくを鳴らしてから、わたしの朱色に染まった頬を両手で包んで、反対側からもしゃもしゃときゅうりを頬張った。あとひとくちでわたしのくちびるに到達する、というところで一度止まって、わたしとしっかり目を合わせてから、がぶりとわたしのくちびるを自分のくちびるで甘噛みしてみせた。
「こどもほしくない?」
なんでそんなことを言ったのだろう。なぜだか目を合わせたときの御手杵のひとみの奥のきらきらに、幸せがすいこまれていくみたいに思えて、今、言葉にしなければ、と思ってしまったのだ。
考えたことないなと、御手杵は答えた。
じゃあ今すぐ考えてと、わたしは多分ヒステリックに言ったんだと思う。もしかしたら叫んでいるようだったのかもしれない。そうしたら、御手杵はふさわしい言葉をまるで持ち合わせていないとでも言いたげに、まゆじりを下げて肩を落とした。
すこしも離れていられないと思う。ほんの半日、声を聞いていないだけなのに、こんな風に立ち止まると、彼の大きな手や優しい目、それからていねいな仕草が眼裏に浮かぶ。好きだ、と思う。今すぐにでも彼のいるあのふたりの家へ走っていきたい。けれども、いますぐに会うことはできない。わたしたちはふたりの関係をこれまでと同じようにうやむやにして、日々をやりすごしてしまう。このまま、離れたままでいいとふたりが同じだけ思うのならば、きっともうそれでいいのだろう。わたしはもう一度まっすぐに伸びる黒い地面のゆらめきときらめきを見つめた。わたしのからだの分だけ、暗く切り取られた影が落ちていた。
スーパーでいつもと同じように夕飯の材料を買って家路に着く。違うのは、わたしが向かう先が友人の家であるということだけだ。彼女は昨夜の急な訪問にも嫌な顔ひとつせずに迎え入れてくれた。
「長すぎた春かねえ」
翌日は日曜日だったが、彼女は仕事だったので早めに布団に入った。わたしは来客用の布団を彼女のベッドの横に敷いてもらった。しばらく誰も使っていなかったらしく、その布団は冷たくてかすかにさみしいにおいがした。
「わたしにはあっという間だったよ」
本当に、本当にそう思った。数年、一緒に住んで、けっこんの"け"の字も出なかったし出さなかったのは、そんなことを考えるひまもないほど、色とりどりに目まぐるしい日々だったからだ。それだけで満足だと思っていた。ほんのすこし前までは。
「落ち着くまでここにいなよ」
ざわつく胸をかかえながら耳をすます。彼女がぽつりと言葉を落とした。
スーパーの袋のなかで野菜やお肉のパックが触れ合って、がさがさとビニールが擦れる音が散らばった。ずしりと重く感じる。肩が落ちて、そのまま手を離してしまいそうになる。固いアスファルトに触れてたまごが割れるイメージが浮かぶ。けれどわたしは手を離さなかった。当たり前のことだった。
ポケットから携帯を取り出して電源を入れる。どっと何通もメールがなだれ込んできて、また彼のまゆげを思い出した。下がった、困ったような、まゆはきっと次の言葉をもう見つけている気がした。
メールは読まずに彼の番号にかけた。数コールののち、彼が電話に出た。受話器ごしにちいさく息をのむ感じが伝わってきて、ああどうしようもないなあと思った。どれだけ頭から振り払おうとしても、もうどうしようもないのだ。
「心配した」
大きく息を吐く音がした。熱くて湿った感じが受話器越しにも感じられた。
「御手杵なんか心配しすぎて胃に穴が開けばいい」
「ひでー」
昨日の会話がうそのように、ふたりの間にはゆるゆるとのんびりしたいつもの雰囲気が戻っていた。わたしがこのあと友人に謝りのメールを入れて、このままあのふたりの家に戻ればもとどおりになれるのだろう。それでいいのか、と思うが、わたしは昨日のことなど忘れてしまったという素振りをすることしかできない。
「なあ、、結婚しようか」
御手杵が言った。わたしは言われた言葉の意味を理解するのに数秒、いつもよりずいぶんと長い時間が必要だった。喉の奥からわけがわからないといった声が漏れて、電話口の御手杵が苦笑したのが分かった。
「昨日の、あの話。正直、こどもは考えたことなかったんだよ。でもなあ、との結婚はずーっと考えてて、いつ言い出そうかなと思ってた。すげえ誤解されたんだろうなあと思ったけど、昨日の俺すげえかっこ悪かっただろ?だから挽回する策を練ろうと思ったんだけど、もういいやと思って」
もういいやと、彼は言った。ずいぶんと投げやりな言葉だが、彼らしい感じがして笑みがこぼれた。やっと笑ったなあと、安堵するような声が続いた。
「先にこどもの話されると思ってなかったんだよ。こどもは……そりゃあいればいいけどな。けど、俺はがいればいいよ。こどもができたらめっちゃくちゃかわいがる自信あるけど、でもがずっと俺の一番でずっと一緒にいてほしいひとだよ」
御手杵が言葉を切った。わたしは視界がゆらゆら揺れるのを感じた。陽炎みたいだ。密度の違う気持ちが混ざり合って、歪んで立ち上ってもやもやして、ひかっている。
「何か言ってくれよ」
彼はまたまゆげを下げて、困っているんだろうなあと思った。昨日の夜から何度も振り払おうとしたけれど、消えなかったその姿は、きっとずっと愛しい景色だ。
「明日また同じこと言って」
御手杵の笑い声が聞こえた。困ったのと嬉しいのとが混ざって、不思議に幸せな響きだった。
明日も、明後日も、来月も、来年も。ずっと。わたしはきみが好きだよ。
theme / おやすみ、明日も愛してる
@saniwan60さまより
(2016.06.15)
material by HELIUM
Close