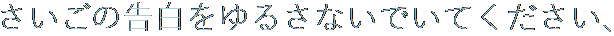
「一期を見せびらかしたかったの」
我が主は近侍を固定せず、当番制をしいていた。彼女の手によって目覚めさせられた順に、規則正しく一日ごとに近侍は入れ替わる。新たな仲間が増えるたび、彼女の近侍を務められる日は遠のいていく仕組みだ。
以前に一度、理由をたずねたことがある。なぜこのような方法をとるのか、と。近侍は厄介な仕事も多く、正直なところ、精神的に幼さの残る兄弟たちには少々荷が重いのではないかと思っていたし、実際に男士たちのなかにも、「面倒くさい」と公言してはばからない者もいた。もちろんその逆に、進んで務めたがる者もいるのだから、そういった状況を汲んでもいいのではないかと思っていた。いわゆる適材適所というやつである。
彼女は同じような質問を、すでにほかの男士から受けたことがあるようだった。開き直った様子で、「だって、やきもち妬いちゃうかもしれないでしょ」とうそぶいたのだ。あんまりにも堂々としていたから、私は苦笑するよりほかなく、追及することを諦めてしまった。
今日は政府との会合と聞いていたが、実際には審神者たちが一堂に会した交流会らしかった。審神者たちは自分と同じような近侍らしき男士を付き従えていて、男士たちは皆一様に、戦闘用でも内番用でもないスーツという畏まった服装に身を包んでいた。似たような恰好をしているのに、当たり前のことながら皆まるで違っている。
我が主は、私をほかの審神者に紹介しながら、すこしだけ得意げに胸を張っているように見えた。珍しく酒を辞していたにも関わらず、幼子のように紅潮した頬が愛らしく思えた。
本来、今日の近侍は私ではなかった。慣れない服の襟元をこっそりと緩めながら、ひとつ息を吐き、疑問を呈したところで、冒頭の彼女の言葉である。見せびらかしたかった、とは存外無邪気な言い回しだ。唇だけで微笑むと、まっすぐに前を向いていたはずの彼女が、「笑わないでよ」などとむくれた言葉を口にした。しかしその横顔は鼻歌でも歌いだしそうだった。
彼女が酒を辞した理由は、私を車でどこかに連れて行きたかったからだとのことである。今日出会ったなかに、何人か気の合う審神者がいたようで、嬉しそうに話を出しながら、彼女の運転する車は軽快な調子で海に出た。
車を降りて近くに行くと、海は月の光だけではない何かによってきらきらと瞬いていた。
海蛍。「ほたる」という名前を冠しているものの、その分類は昆虫ではなく甲殻類とのことだ。砂浜を裸足で歩きながら、前を歩く彼女がしたり顔でそう説明した。振り向いた彼女の白い頬は、ぼんやりとまあるく光っていた。
「今日は付き合ってくれてありがとう」
「いえ、お安い御用です」
「一期くらいだよ。そんな風に言ってくれるの」
「…長谷部も同じようなことを言うと思いますが」
「長谷部くんは…なんか違う」
そう言って彼女は、おかしそうに笑った。長谷部が聞いたら肩を落としそうな発言だったが、ここにはふたりきりなのだから問題ないだろう。私も彼女につられて笑うことにした。
首筋を撫でていく風は、すこしだけ春の温度をふくんでいる。それでも冷たいことには変わりないから、私はジャケットを脱いで彼女の肩にかけた。彼女は今日一番の微笑みを描いて、ありがとうと言った。
彼女の周りはいつも軽やかで心地のよい空気が流れている。きっと多くのことに気を配り、頭を悩ませ、胸を痛めているに違いないのに、彼女はそれを億尾にも出さず、いつもたおやかに笑っていた。芯の強い、どこか遠くを見つめる瞳を、私は好ましく思っていた。ずっとそう思っていたが、それを口にすることはできなかった。私にとっては何よりも難しいことだった。
彼女のポケットから鍵が滑り落ちた。水面と同じようにきらきらと輝きながら、ちいさく音をたてて砂に着地する。あんまりにも奥ゆかしい様子だったから、彼女はそれに気づいていないようだった。また歩き出した彼女の後を追いながら、さりげない動作でそれを拾い、ポケットにしまい込んだ。
「前にさ、一期が聞いてきたことあったよね。何で近侍は当番制なのかって。ほんとは、私一期のそばが一番落ち着く。けど、一期は近侍ばかりじゃ退屈しちゃうかなと思って」
語尾はちいさくかすれて、ともすれば聞き逃しそうな頼りない響きでもって、私の鼓膜を揺らした。主は振り向かず、大股でゆっくりと砂に足跡をつけていく。彼女の精いっぱいの歩幅は、私にとっての一歩とほとんど同じで、その身を捉えるのはひどくたやすい。
彼女の髪をすいた風が、私のもとまで届くと、濃い潮のかおりにまじってみずみずしい果実のような甘いにおいがした。風にかきあげられ露わになった耳は熱く色づいていた。
「なんてね。びっくりした?」
くるりと身を翻した彼女の瞳はまるきり凪いでいて、からかうように細められていた。にんまりと唇が弧を描き、私の期待をまるく包んで閉じ込めた。
「主も人が悪い」
「一期が焦るとこ見てみたかったのになー」
不満げに唇を尖らす彼女に、私は安堵ともつかぬ複雑な胸を抱いたまま、取り残された気分になった。「さて帰りますかー」とポケットを探る彼女の顔面が青ざめるのを見届けて、口のなかで笑いをかみ殺す。
「どうかされましたか?」
「ない…」
「と、言いますと?」
「鍵!どうしよう、ない!どこかで落としたのかも…」
瞳がにわかに荒れ出して、私はついに噴き出してしまった。怪訝そうに眉を顰める彼女に、くくっと喉の奥を鳴らしながら、ポケットからさっき拾った鍵を取り出してみせると、彼女は呻きとも悲鳴ともとれる声を上げた。それが余計に私のツボをぐいぐい押してくる。笑いのつぼを、である。
「一期がこんな人だったなんて…!」
「先程の仕返しですよ」
「え」
「私は主のそばが一番落ち着きます」
「え?!」
「特に先程のような面白いお顔をされたときなど、とても」
くつくつと収まりきらない笑いは零れ続けた。寄せては還る波のように、ひいてはよみがえりそうな予感がしていた。
主は私の手から奪うように鍵をとると、情緒もなにもない力強い足取りで車へ向かう。その背を追いながら、私は彼女と自分の言葉を反芻していた。いつか、彼女に本来の意味で告げることもあるだろうと思いながら。
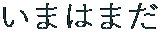
刀剣乱舞企画「茜さす君が袖振る」さまへ提出
(2016.05.04)
material by 100g | title by 月にユダ
Close