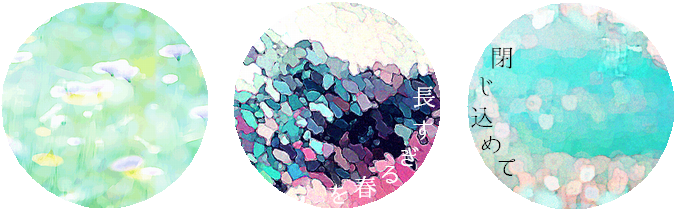
おおきなあくびをしながら食堂に顔を出すと、いつもの席に座るの様子がおかしいことに気が付いた。かすかに桜色に染まった肌が妙に色っぽい。いつかの夜に組み敷いたの肌けた着物の向こう側を思い出し、朝っぱらだというのにくるものがあった。
よこしまな感情を追い出すように頭をふって、のとなりの定位置に腰かける。近くまで来てみると、当然のことながらどうもそういう艶っぽい事情ではなさそうだということが分かったからだ。
「具合悪いのか?」
小声でそう問いかけたが、荒く呼気をはずませているというのに、はゆるゆると首を横に振った。しかし、そこにはいつもの凛とした表情はなく、こわばってうまく笑みもできない、幼い少女のような顔だけがある。
「うそつきは泥棒の始まりらしいぜ」
「別にうそなんかついてない」
「強情だなあ。熱あるんだろ?」
「……なんで?」
「毎日隣で見てる顔なんだから、分かるに決まってる」
の額に手を伸ばす。嫌そうに顔をしかめられたが、構わずに確かめるようにふれた。そうしたら、手のひらにじんわりとした熱が伝わってきて、ほれ見たことか、と目を細めながら彼女を見やると、ひどくばつの悪そうな視線が飛んできた。そのひとみは憂鬱な熱を帯びていて、かすかに潤みで混濁しているようだった。
迷わずの手をとり席を立つ。台所に顔を出し、光忠に粥を頼んだら、彼は一瞬目をまるくしたのち、俺に寄りかかるようにして辛うじて立っているを認めたらしく、すぐに快諾してくれた。
・
・
「大丈夫なのに」
無理やり自室の布団に放り込み、口まで埋もれるほど深く布団をかぶせた。は居心地わるそうにもぞもぞと布団から顔を出しながら、唇の先から小さな声をもらした。
あきらかに責めるような言葉なのに、ずいぶんとよわよわしくかわいらしい。ははっと軽く笑うと、ますます嫌そうにのひとみが歪んだ。
「大丈夫じゃないからこうなってんだろー?」
「なってる、じゃなくて、御手杵がそうしたんでしょ」
「そりゃそうだけど。今日一日くらい休めよ」
「でも……」
「あんたがみんなの前で倒れたりしたら、阿鼻叫喚だぜ?」
「う……」
「今日一日は休むこと。俺があんたを見張っといてやるよ」
にっと唇の端で笑みを作ると、は観念したようにからだを深く布団に埋めた。
「ごめんね。……ありがと」
「おーおー、珍しく素直だなあ」
「……御手杵は私を休ませたいの?怒らせたいの?」
「悪い悪い。ゆっくり休んでくれよ」
ちょっと粥でもとってくるな、と腰をあげようとしたら、ずいぶんと奥ゆかしいちからで制された。布団の横から伸びた彼女の手が、俺の上着を遠慮がちにつかんでいる。
思わず顔がゆるむと、が、にやにやしないでよ、とどうやら熱のせいだけではなさそうな顔色でふてくされている。
俺はどうしてもにやけてしまう口もとを片手でおおいながら、もう一度、今度はもうすこし彼女の近くに座り直した。
「少し寝るか?」
「うん」
「俺はここにいるから。ずっと」
「……うん」
そう言って、が存外素直にまぶたを落とす。頭をなでてやると、猫のようにちいさく声をもらし、しばらくすると静かな寝息が聞こえてきた。
俺は再度布団を彼女の口もとぎりぎりまでかぶせてから、一息つく。
時たまが憎くなる。
単なる槍だった頃、俺はこんな風に胸を痛めたことはなかった。そりゃあ多少の思い出はあるが、こんな風にひとりのもろい人間とかいう生き物に執着したことはなかったのだ。
あんたはいつまで俺のそばにいるのだろうか。俺はいつまであんたの笑う顔を見てられるのだろうか。
以前にそんなようなことを冗談めかしに尋ねたら、は妙に挑戦的なひとみをして、ずっとよ、とはっきり言い切った。俺はそれを信じたいと思っているけれど、こんな風に弱った彼女を見ると、途端に不安になってしまう。我ながら随分と女々しいものだ。
付喪神と人間の生きる長さは、絶対的に異なっているだろう。きっと俺にとってのの一生は、ちいさな飴玉のひとつぶを舐めきるくらいの長さでしかないのだ。
それでも、それでも。俺は彼女の言葉を信じたつもりで、ずっとそばにいる。がそこにある限り。
障子からもれる光が、あたたかく傾いていくのが見えた。
副題 / それはまるで飴玉のようで
@katasani1hourさまより
(2016.04.10)
material by moss
Close