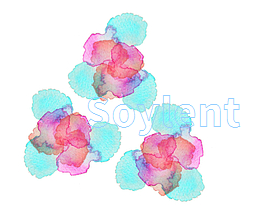
彼が私を抱くのは、寂しくて一人でいられないときだけだということくらい、もうとうの昔に分かっていた。それから、それを問い詰めてしまえば、この危うい関係性はいとも簡単に壊れてしまうことなど、ひとに言われるまでもなく。
「は子どもみたいだな」
ロイがじゃれつくように私の髪にその細い指を通していく。彼が、私に触れる前に、あの白い手袋を外す仕草が好きだった。
私は彼に背を向け、じっと毛布を握りしめながら目を閉じる。
彼に抱かれたあとは、彼の分の毛布まで奪うみたいに包まって、それだけを抱きしめて眠る。彼に抱き付き、彼の胸に顔を埋めながら瞳を閉じることができれば、どれだけか幸せかと思う。もうその瞬間死んでしまってもいいかもしれない。
朝にはいなくなっているひとの息遣いを、背中越しにかすかに感じながら思う。
私はきっと、この傲慢で打算的な寂しがり屋の飼い猫なのだ。心から甘える素振りでエサをねだる。良い頃合いを離れて歩く。時には冷たく突き放したりしながら、気まぐれを装った、忠実な飼い猫。
自己中心的な野心家は、溺れそうな私に手を差し伸べることなく、その様をほとりから眺めている。それが、私と彼の最も正しい距離なのだ。
「ロイの方が子どもみたいよ」
「おや。おかしなことを言うな、君は」
喉の奥で隠すように、ロイがくつくつと笑う声がする。私は必死で目をつむる。背中ごしでも脳裏に浮かんでくる彼の上手な笑顔にすら目を背けるために。私はきっとその顔を思い出すたびに、彼の手を離せなくなってしまうからだ。差し出されもしない、冷たい指の先でもいいから、彼を離したくないと思ってしまう。
「我儘な子どもよ」
「…そうかもしれないな」
ぱさりと私の髪の毛がベッドの上に落とされた。ロイの手が私の腕を触れるか触れないかの距離でつたいながら下腹部へと下りていくのを感じる。
体温の低い彼の手は、いつも冷たかったけれど、最中に私に触れているときだけは、まるで指先から炎でも出しそうなくらいに熱かった。手だけではなく、その唇も体も視線も。けれども、先ほどまで私の体中を這っていたその指は、もうすっかり熱を失っていて、おなかの下あたりにたどり着いた瞬間、ぞくりと肌が粟立ったのがはっきりと感じられた。
まるで彼の言葉みたいだ、と思った。
女性を喜ばせることを生業としているみたいに振る舞うくせに、昨日酒場で会った美しい歌姫には言ったであろう言葉を、私に向けてくれたことは一度もない。戯れでもいいのに。
「私を愛してる?」
「どうしたんだ、」
「…それとも愛してない?」
ロイのもう片方の手が私の腰に回った。無言でそのままゆっくりと彼の方へと引き寄せられる。
「まだ分からない?」
耳の中に落とし込むように、かすかに掠れた声で彼がそう言った。
求めている言葉をきっと今日も、そしてこれからも彼が与えてくれることはないのだろう。そう思うと、閉じていた瞼が勝手に熱くなった。
素肌に触れるロイの指が、また段々と上に上ってきて、片手で私の胸を捉え、もう片方の手で私の喉元を掴んだ。少し力を加えてくれれば、きっと私は息をしなくなる。
力強く胸をもまれ、先端をつままれれば、体はどんどん熱くなった。それでも喉元の手はただ柔らかく私の魂を握っている。本当にほしいものが、手に入らないのならば、いっそのこと私の魂を握りつぶしてほしい。
「私は壊れない玩具じゃないのよ」
私の喉元に添えられたロイの手に、少しだけ力がこもった。
「随分と人聞きの悪い言い方をするんだな」
冷ややかな声が落ちて、彼がすぐに力を緩める。その手はそのまま私の体を這いながら、下腹部へと移っていく。その動きには何の色も感じられない。
水音が響く。耳元でロイの熱い吐息と、それから抑えるように漏れる冷ややかな嘲笑が聞こえる。
「私は…あなたが望むような女になれないのよ」
「そんなことはないさ」
彼の指が私のなかに埋められ、ゆっくりとかき混ぜられる。頭のなかが混濁して、まばたきのたびに目尻から雫がこぼれていく。
「そうやってあなたは私を縛りつけるから、」
ロイは私の好きな笑い方で喉を震わせたあと、全部私のせいにすればいい、と低く呟いた。ひどく残酷な声音で。
彼の指が私の全てを犯すように暴れ出す。唇が先ほどまで掴まれていた首筋にきつく跡を残す。慣れた手つきは私を追い立てて、どこかへ連れ去ってしまう。
隙間を埋め尽くすように。
全てを歪ませてしまうように。
「お願い…さよならと言わせて」
「…君を手放すつもりはないよ」
零れ落ちた彼の言葉を本心と思えるほど私の心が純粋であれば良かった。
(2016.05.29 remake)
material by 鯨のまにまに
Close