ちょっと目を離した隙にすぐこれだもんな。深いため息が漏れる。ドアのすぐ横に備え付けられている革製の茶色のソファーに腰かけて、膝に書類の山を乗せて一息つく。愛すべき上司であるホークアイ中尉は今日、久々の休暇をとっていて、家でブラックハヤテ号を甘やかせてあげるのだと昨日とろけるような笑顔で言っていた。仕事中には滅多に見せないその表情を思い出し、無意識に頬が緩む。最も、見せない、というよりは、この部屋の主の"おかげで"それどころではないのだろう。しかし、そんな中尉くらいしか、その人をまともに働かせることができないのだから、私自身もふがいないものだ。
複雑な思いで視線をデスクに向ける。ぼーっと見つめていると、一瞬、椅子のキャスターがかたっと小さく音を立てた。座ったことはないが、見るからに重量感のあるそれは、風くらいで動くような代物でもないだろう。昨日休暇前にもう一つ、中尉が教えてくれた「大佐操縦のコツ」の内の一か条が脳裏に蘇ってきた。
「敵は意外と身近に潜んでいるものよ」
疲労で少し霞みがかった頭を起こすように横に振り、今度は「ぼーっと」ではなく、注意深く見つめてみる。すると、机の隙間からよく見慣れた青い布地がはみ出しているのが見えた。まったく、あの人は30間近になってもこんなことしているなんて、恥ずかしくないんだろうか。再び零れそうになったため息をぐっと飲み下し、書類を抱えて立ち上がった。
あー、大佐ってばどこ行っちゃったのかなー!
わざとらしく大声で言って、どさりと乱暴に机の上に書類を乗せた。すると当然のようにそれよりもずっと前からいた住人たちが、はらはらと床に舞い降りていった。私は椅子の横に回り込み、書類を拾おうというフリを続けた。腰を曲げて机の下を覗き込む。案の定、私の視界は丸まった青い物体を捉えた。黒髪がさらりと落ちて、その間から現れた瞳とばっちり目が合う。
「君は本当に勘がいいな」
「中尉のおかげです」
襟元を緩めながらすごすごと机の下から大佐が顔を出した。いたずらっこのように無邪気な表情。何事もなかったかのように椅子に腰かけ、私が散らかしてしまった書類たちを拾い集める様を優雅に眺めている。
「もう少し短いスカートだったら、より良い眺めになるのだが」
「力の抜けることを言うのはやめてください・・・」
「あいかわらずつれないな」
大佐がふっと息を漏らす。一体誰のせいだ、誰の。私は声に出さずに一人で文句を垂れ流しながら、しゃがみこんで書類の端を床の上で整えた。至近距離からの視線を感じて顔を上げれば、大佐が視線を合わせるようにしゃがみこんでいた。彼の口角は綺麗なカーブを描いていて、街中の女性陣がきゃあきゃあ言うのも無理はないな、と妙に冷静な頭で思った。
「は私にだけ随分つれないようだな」
「・・・ほんっと、見境ないですね大佐も」
黒い漆黒の瞳がこちらをまっすぐ見据えている。その瞳に私だけが映っていることに驚いて腰が引けてしまったが、気づかれないようにわざと軽口をたたいた。察しの良い憎むべき上司には、私のごまかしなど通用しないかもしれないが、そうせずにはいられなかった。人を見透かすような目から逃げるように、瞳を落とす。大佐も何も言わずに動かない。こんなところを誰かに見られたら、どんな噂を立てられるかと思うと気が気ではない反面、目の前の人が何を考えているのか、そのことが気になっていた。
とはいえ、彼がこんな風に私をからかうのは今に始まったことではなく、彼にとってはもはや日々の日課のようなものかもしれない。初めて彼の下についたときから、変な人だと思っていたが、その感情に別の色が足されるのにそれほど時間はいらなかった。今現在の私の彼に対する気持ちは、自分でも理解不能な不思議な色をしている。
「どうした?」
低く甘い響きが、まるで耳のすぐそばでしたようだった。どこかでこういう風に女の人を騙すのか、などと考えてしまう自分が恨めしい。それから大佐が。
机の影になっているためか、光の入ってこないこの場所は昼間にしては少し暗い。それでも視界の中央に陣取る大佐の影だけは、薄い影のなかでひと際黒く輝くように見えた。まるで彼の瞳のように。その影が揺らめいて、近づいて私の腕をつかんだ。震えるなと全神経に伝達したというのに、さっきかき集めた書類はするりと手から零れ落ちていってしまう。
何のおつもりですか。
精いっぱいの強がりを込めて、彼の瞳を見据える。じわりと何かが込み上げたが、唾液と一緒に飲み込んだ。ごくりと喉が鳴った。
「まるで理解に苦しむ、という顔だな」
「そうですね」
「君の考えていることと同じだよ」
大佐の漆黒の瞳が薄く細められる。その笑顔が慈しむように見えてしまったのは、きっと見当違いの私の自惚れに過ぎないのだろうけれど。
大佐の低い体温が、掴まれた腕から伝わってくる。私の体温を分けてあげたいと思った。掴まれていない方の手を彼に伸ばしかけたとき、不意に廊下からの靴音が私の鼓膜を振動させた。一定のリズムを刻みながら、段々とそれは大きくなっていく。
「とりあえず離してください」
「さあ。どうしようか」
「ちょっと、大佐、ふざけてる場合じゃ」
言いかけて、腰に腕が回ったと思ったら抵抗する間も与えられずに一瞬にして引き寄せられ、気づいたときには彼の腕のなかだった。全身が急激に熱を上げていく。耳元で、「どうせハボックだ」という彼の無機質な声がした。大佐が喉の奥を小さく鳴らす。
「いや、ハボックでも十分まずいと思いますし、状況悪化してますし!」
「ふむ。どうも君は冷静すぎていけないな」
「十分冷静じゃないんですが!」
両腕で力いっぱい彼の体を押し返してみてもびくともしない。大佐はいよいよ楽しそうに声を出して笑った。先ほどから聞こえていた靴音が扉の前で途切れ、私ははっとして息を呑んだ。大佐は多分微塵も焦ったりしていないだろうことが、余計に私を苛立たせていた。ドアノブががちゃりと音を立てて、きいと扉が軋む音が続く。
「またいないのかよ・・・」
呆れとか億劫さとかがないまぜになった声。大佐の言った通り、靴音の主はハボックだった。私と大佐のいる場所は扉からは死角になっていて見えないようだ。安堵して腕に込めていた力を緩めてしまったが、はたとすぐに自分の置かれている状況のまずさを思い出した。面倒くさがりやだが、面倒見のよい同僚は、おそらくこの状況を見ても言いふらしたりはしないだろうし(ハボックなら自分から言いふらして質問攻めに合うのも面倒くさいとか思いそう)、こうなったら彼に助けを求めるのが一番良い。
息を吸って大声を出す準備をする。瞬間、大佐の手が伸びてきて、右手で私の口を塞ぎながら左手の人差し指を自分の口元に寄せた。私の意図するところはとっくに読まれていたというわけだ。深いため息とともに扉の閉まる音が響いた。
それを聞き届けてから、「言った通りだったろう」と得意げに言って、大佐が私の口を解放した。
「論点がずれてるとかって思いません?」
「思わんな」
自信たっぷりにそう言ってのける彼に、私はほとんど呆れてしまっていた。腕のなかにいることにも妙に慣れ出してきてしまっている自分がかわいそうになってくる。
「誰にでもこういうことをされないなら、大佐はもっと女性におもてになるかと」
顔を上げて、控えめに顎を引いて大佐の漆黒の瞳を見つめる。少しでもどちらかが意図すれば、すぐにでも唇が触れ合ってしまいそうな距離だった。大佐はまたふっと息を漏らして笑い、同じように目を細めてこちらを見た。憎らしいほど綺麗な笑み。
「その”女性”のなかにが入るのならば考えてみようか」
大佐はそう言って、私の瞼に唇を落とした。
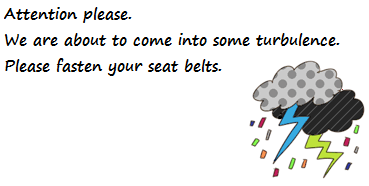
過去作を加筆修正。セクハラ上司はその後の軍部シリーズに続きます(2016.02.16)
material by マグロノマルセイ
Close