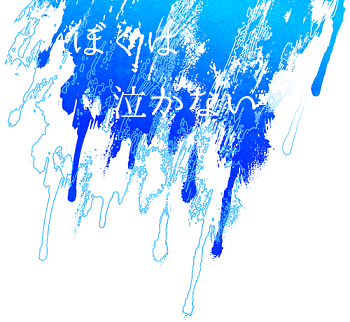
「またですか」
「うん、だって、私のこと好きらしいし」
さんが肩を竦めて言った。その顔は嘘みたいに幸せそうで、僕は何も言えなくなってしまう。こんな会話をするのは、今年だけでも何度目か分からない。僕は今みたいな始まりとその後に必ず訪れる終わりには、いつも彼女のそばにいて繰り返し同じような台詞を吐いた。まるでお決まりの芝居みたいだ。始まりは彼女の好きな濃いピンクの色をしたハーブティーを、終わりには甘いココアを差し出す。僕の部屋の水玉のマグカップはそのためだけに存在している。彼女はそれに一度だけふっと息を吹きかけて冷ましたフリをして、そのあと必ず小さな火傷をする。僕に冷たいミネラルウォーターを求め、グラスに舌を揺蕩わせながら、笑ったり泣いたりするのだ。いつもいつも。それからしばらくして温くなってしまったハーブティーかココアを飲み、もったいぶったような笑みを浮かべる。僕の目を見ながら。
「さんは何度俺に同じことを言わせれば気が済むんですか?」
「さあ?わかんないよー。私のせいじゃないもん」
長太郎が飽きるまでかなあ。彼女はそう言うと、熱いハーブティーに一度だけ息を吹きかけ、マグカップから立ち上る真っ白い湯気を揺らした。僕はその恒例の儀式を見届けずに、さっさと冷蔵庫へ向かう。冷やしておいたミネラルウォーターをグラスに注ぐために。作り付けの背の高い食器棚からグラスを取り出したとき、背後から「あちっ」といつもの声が聞こえた。本当に学習しない。彼女も、僕も。
僕の一つ年上の幼馴染は彼女の学校で有名な「軽い」女の子らしかった。頼めばすぐにやらせてくれるという噂が流れていると、彼女の学校に通う知り合いから聞いてしまった。ただ、本人曰く、「それは最後の切り札」なのだそうだ。だから彼女に言い寄ってくる男はみんなそれを目的にしているのに、彼女は切り札だと思っているので、そのあたりの意見の相違が彼女の恋を短命にしている原因だ、というのが僕の持論。根本的な問題はもっと別のところにあって、何度か指摘もしたのだが、彼女は瞬間耳を塞いで話を聞かなくなる。あくまでも「愛」を疑いたくないらしい。アホくさ。
「今度の人こそ違うと思うの」
「はあ」
「もちろん元彼も私のことを好きだったとは思うんだけどね」
そう言って、彼女はまた舌はグラスの水のなかへ飛び込ませた。まるで水と踊るみたいに舌が動く。上目遣いで僕を見ながら無邪気を装って繰り返されるその動きは、何度も何度も見せられているはずなのに、僕はいつもどうしても直視することができない。赤い舌が上下しながら透明なドレスを着脱する。
気づかれないように目を逸らした。彼女はどうしようもない自己防衛本能に基づくおはなしを始めたようだった。僕はそれに適当に相槌を打ちながら、思考を遠くに飛ばす。昔の、こととか。
僕がまだ彼女のことを「ちゃん」と呼んでいた頃、僕らはよく二人で短い旅をした。それぞれの母親にお弁当をねだり、良く晴れた日曜の朝、僕は自転車で彼女を迎えに行った。なぜだかいつも少しの緊張を指先に絡ませ、インターフォンを鳴らしたことを覚えている。扉の向こうからどたどたとおよそ女の子らしくない足音が聞こえて、扉が開くと頬を薄く桃色に染めた小さな彼女が、頬と同じ色をしたリュックを背負って現れるのだ。その瞬間がたまらなく好きだった。
「遅いよ、長太郎」
ちゃんはずっと僕のことを「長太郎」と呼び捨てにしていた。年上ぶりたいような生意気な口調なのに、甘えるような眼差しも昔から変わらない。彼女は少しも変ってくれない。周りも、僕も、少しずつ変わっていくのに、彼女だけが取り残されているように思った。
自転車を漕いで、僕たちは目的もない旅を楽しんだ。知らない道を進むことに、僕はいつも躊躇ったが、彼女はひとつも怖いことなんかないような顔をしていた。どこか適当な場所でお弁当を広げて二人で食べた。僕がおにぎりなら彼女はサンドイッチ。逆もしかりだったので、僕らは取り換えっこしながらそれらを頬張った。僕らの親はきっとどこかで示し合わせていて、その光景を想像していたに違いない。真っ青な空の下、それは目が眩むほど幸せな光景だ。でももう二度とそこに行くことはできないこともわかっている。
帰り道。幸いにして僕が子供にしては道を覚えるのが得意だったから、旅のあとに迷うことは一度もなかった。彼女ひとりだったらどうしていたのか。このことを一度彼女に聞いたことがあった。彼女は「迷ってもいいって思ってた」と言った。珍しく甘えのない真っ直ぐな瞳は、しかし黒い影を帯びていて、その奥の光を僕には見つけることができなかった。誰にでも愛されて、誰にも愛されない。深くて暗い、美しい瞳。
「長太郎聞いてるの?」
「はいはい、聞いてますよ。で、彼がどうしたんですか?」
彼女はマグカップを大事そうに両手で持って、もう温くなってしまったらしい濃いピンクの液体をずずっと行儀の悪い音を出しながら啜った。水の入ったグラスはテーブルの上に放置されていて、少しだけ汗をかいていた。
「そう。だからね、彼は違うと思うの」
長太郎もそう思うでしょ。そう言った彼女は、僕に肯定か単なる頷きのみを求めているようで、僕はそんなわけないだろ、と内心毒づきながら、頷いて「そうですね」と笑ってやる。そう言うと、さんは嬉しそうに微笑んで、僕が彼女のために淹れたハーブティーを啜るのだ。
僕はあと数日か数週間のうちに、彼女にココアを淹れてやるだろう。それは彼女の瞳と同じくらい甘くて、ひどい味がする。
過去作を加筆修正。長太郎くんは不憫がよく似合います(2016.02.03)