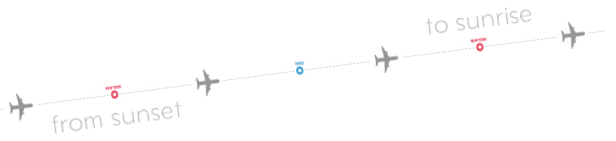
「最近、調子はいかがですか?」
ギルさんに言われてなにげなく尋ねたその言葉に、大した意味はなかったのに、電話口でルートさんが言葉を失っているのが分かった。何かおかしなことを口走っただろうかと、その前の会話を反芻してみたが、全く心当たりがない。単なるあいさつと、ちょうどギルさんが日本に来てますよ、という彼も確実に知っているであろうことを、話のネタとして報告しただけだ。
「あ、あの……?」
「あ、ああ、すまない。仕事は順調だ。特に問題はない」
「そうですか」
わざわざ"仕事は"と強調されたような気がする。となると、プライベートに何かあったのだろうか。しかもそれはわたしに聞かれたくないことなのだろうか。そう思うとなんだか寂しい気持ちがわき起こって、ついさっきのルートさんと同じように、口を閉ざしてしまっていた。
ギルさんがこちらに来るという話を聞いて、もしかしたら彼の弟も一緒なのではないかと期待していたのだけれど、やはり彼の優秀すぎて多忙な弟は、仕事の都合で来られなかったらしい。あからさまに落胆してしまったのか、ギルさんはあの独特な嫌味のない笑い方をしたあと、電話してみろよ、と提案してくれたのだ。
久しぶりに聞くルートさんの声は、電話越しでも容易にわたしの心臓をつぶす。どきどきしながら、そしてすこしだけ彼が喜んでくれないかと夢想していたが、このありさまだ。喜ぶとか喜ばないとか、そんな次元ではないらしい。
「すみません。お仕事の邪魔でしたよね」
ごまかすように明るく言ってみたが、そのあとに続いた笑いは妙に乾いていた。慌てて、それじゃあ、と通話を打ち切ろうとしたのだけれど、ルートさんの声がそれを制止した。あー、とか、うー、とか、彼にしては珍しく意味をなさない言葉だったような気がする。
「いや、邪魔なわけではない」
「でも……」
やはり切った方がいいのではないかと続けようとしたが、私のその言葉に割り込むように、今度はルートさんが尋ねてくる。
「は最近調子はどうだ?」
「えっ……あー……いいですよ、絶好調です」
なんとか空気を和まそうとおどけてみたのに、何が悪かったのか向こう側の空気がぴしりと凍り付いたのが分かった。受話器から冷気がもれてきたような気がして、びくりと肩が震える。
「それは、プライベートが、という意味か?」
「えっと、そうですね。仕事もプライベートも順調です」
「そうか」
「ルートさん?」
なんだか、何かがかみ合ってない。そんな気がして、確かめるように彼の名前を呼んだ。いつもの落ち着いた声は、自嘲気味な笑いを一つもらした。
「その……幸せ、なのか?」
「へ?」
「いや、だから……恋人ができたのだろう」
「は?……え?いやいやいや!そんなの!できてませんよ!」
「え?」
「な、なんでそういう話になるんですか?!」
私が声を荒げると、襖が開かれ、にやにやしながらギルさんが部屋に入ってきた。聞かれてたのか!と怒るべきだったのかもしれないが、とにかくルートさんの言っていることの方が分からなくて、私の頭は混乱していた。だから、そのままギルさんが半ば強引に私の手から受話器を奪ったときも、さほど抵抗できなかった。というか、ほとんどされるがままだった。
ギルさんは笑いを押し殺しながら(実際はもうだいぶ笑ってたけど)、ドイツ語で何がしかを話していた。ルートさんの低い声が、一度受話器からうなるように響いてきたと思ったら、ぽんと受話器が手のなかに戻ってきた。ギルさんはそのまま、部屋に入ってきたときと同じように愉快そうな表情をしていて、くるりと踵を返してまた部屋を出て行った。
「……もしもし?」
「すまない」
「ど、どうしたんですか?」
申し訳なさそうな、弱り切ったルートさんが言うには、彼の国では、仕事とプライベートの調子を聞くとき、プライベートとはほとんど恋愛のことを差すらしい。どうやら私は意図せず、いやむしろギルさんにそそのかされて、ルートさんの恋愛事情を聞き出そうとする下世話な人間になってしまっていたみたいだった。
先ほどギルさんが出て行った襖を睨みつけてみても、ルートさんに何と言って謝ればいいか分からなかった。
「本当にあの人は……すまない」
「ルートさんが謝ることじゃないですよ!」
「いや、そもそもがそんなことを簡単に聞いてくる人間じゃないってことを思い出すべきだったな」
ルートさんが苦笑する。耳もとに降ってきた呼吸の温度まで感じられてしまう気がしてどきりとした。ああ、これだから電話は苦手なのだ。
「……ルートさんはわたしに恋人ができていた方が良かったですか?」
「何でそうなるんだ」
「だって、幸せなのか?って」
「それは、には幸せになってほしいと思っているからな」
至極当たり前のことだ。だけど、わたしは"ルートさんに幸せにしてほしい"のに、彼にはまったくそんな気がないことが悲しかった。分かってはいたけれど、彼にとってのわたしは、あくまで友人の妹でしかありえないのだ。
「ありがとうございます。頑張りますね」
「……別に頑張らなくてもいいんじゃないか」
「何なんですか、それ」
「いや、ただ……」
ルートさんはまた言い淀んだ。短い沈黙。耳元で大きく息を吸い込む空気の音がした。
「明日、そっちに行ってもいいか?」
「……へ?」
「ああ、こっちの明日だから、たぶんそちらの二日後になるか」
「いや、そういうことではなくてですね……お仕事、大丈夫ですか?」
本当は会いたい。ものすごく会いたいけれど、唐突な申し入れに驚いてしまって、妙な気遣いの言葉が先にこぼれてしまった。すごく嬉しいって伝えればよかったな。そう思いながら、それでも彼を困らせてしまうのが怖かった。
受話器越しにふっと柔らかい息が漏れる。目もとが緩んで、控えめに口角の上がる。いつも眉間に皺を寄せて難しい顔をしている彼の、笑った顔がたまらなく好きだ。ああ、今彼が目の前にいたらいいのにな。
「言っただろう?」
珍しくおどけた声音。
「仕事は順調だ。問題ない。……ただ、俺が君に会いたい」
ルートさんはそのあとすぐに大きく咳払いをして、じゃあ明後日、と一方的に通話を打ち切ってしまった。わたしはというと受話器を握りしめたまま、のぼせたみたいに靄がかかった頭で明後日どんな顔をして会えばいいかへたり込んで考えていた。それはきっと彼も同じだと思えるから、余計に困ってしまうのだ。
(2017.04.29)
material by FREE LINE DESIGN
Close