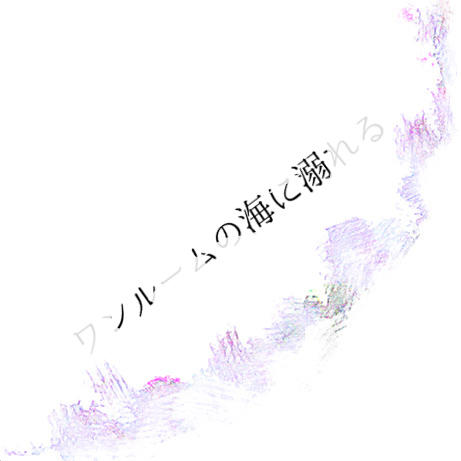
「お風呂、沸きましたよ」
前髪をヘアピンで留めたルクセンくんが洗面所から顔を出した。白いチューリップのモチーフがついたそのヘアピンは、私用に彼の家に置かせてもらっているのだけれど、最近はすっかり彼のお気に入りになっているらしかった。確かによく似合ってる。私は散歩から帰ったばかりの老犬のように、ソファーにだらしなくうつぶせに寝転がったまま、「じゃあ、先に入っていいよ」と軽く手を振った。そのままその手を机の上のグラスに伸ばす。しゅわしゅわと泡立つよく冷えた炭酸水は、さっきルクセンくんが入れてくれたものだ。
記録的猛暑日になるでしょう。ペールカラーのサマーセーターが良く似合うお天気お姉さんがにっこり微笑む顔が思い浮かんだ。そうだ、今朝のニュースでそう言っているのを見て、私はルクセンくんにデートプランの変更を申し出ようか迷ったのだ。けれども携帯とにらめっこしている内に待ち合わせの時間が来て、結局当初のデートプラン通り、私たちはウィンドウショッピングをたっぷり楽しんだ。平日は朝と夜の時間帯に家と会社を往復するくらいしか外出しないせいか、私は多分"夏"というものを少し舐めていた。久々に浴びた優しさなど一ミリも感じられない日中の日差しは、日傘をしていても肌を焼かれているような気分になったし、せっかくルクセンくんのために施した濃いめの化粧は、ものの1時間程ですっかり流れ落ちてしまった。
「お風呂、沸きましたよ」
ルクセンくんが珍しくわずかに語気を強めた。頭だけで見上げると、視界はいつのまにかルクセンくんの影に覆われてしまっていた。反射的にびくりと肩がわななく。持っていたグラスから炭酸水が零れて手の甲を濡らした。慌てて飛び起きようとしたのに、ルクセンくんがグラスごとわたしの手掴んで、べろりと赤い舌で濡れた私の手を舐めた。
「な、なに!?」
「お風呂、沸きましたよ」
「え、あ、それはさっき聞こえたよ。だから先に入っていいよって言ったんだけど、聞こえなかった?……うひゃあ!」
ルクセンくんが私の手からグラスをはがして、まだ濡れていた親指を口に含んでいる。思わず手を引くと、軽く歯を立てられた。第一関節を甘噛みされたまま、生ぬるい彼の口内で水っぽい舌がゆるゆると動くのを感じる。ぞわぞわと背筋が粟立っていたたまれない。チューリップのヘアピンをしていても、ルクセンくんはやっぱり恐ろしく男前なのだ。
「一緒に入ろうって、言ってくれないんですか?」
名残惜しそうに卑猥な音を立てて私の親指を解放してから、ルクセンくんが上目遣いに尋ねてきた。ぬらぬらと濡れた親指を眺めると、かすかに歯型がついているのが見えた。
「やだよ!」
「どうしてですか?」
「恥ずかしいし」
「の裸ならいつも穴があくほど見てますよ」
「そういう問題じゃないし、それはそれでどうかと思う……」
力なくうなだれる私を、ルクセンくんが幼子のように純粋な疑問をたたえた瞳で見つめてくる。何で空は青いの?そんな風に、答えられない質問を突き付けられているみたいな気持ちだ。だって、ベッドの上での裸とそれ以外の場所の裸は違う、と思うのだ。これは多分とても主観的な感覚の問題だけど、そもそもお風呂はとても明るいじゃないか!
「……答えられないなら連れて行ってもいいですか?」
「だめです」
間髪入れずにそう答えたのに、ルクセンくんはまるで聞こえていないという風に眉ひとつ動かさずに私の体の下に腕を差し入れて、そのままひょいと抱きかかえられた。それこそ間髪入れずに、だ。
「ちょっと!」
じたばたと手足を動かして暴れてみたが、ルクセンくんはその細い腕のどこに隠していたのと聞きたくなるくらい力強くてびくともしない。それどころか私の首元に顔を埋めて、べろりとそこに舌を這わせてくれた。浅い息が漏れて顔に血液が集まってくる感じがした。ルクセンくんは満足げに自分で濡らした私の肌に息を吹きかけた。
「しょっぱいですね」
顔を上げたルクセンくんはそう言って、いつもより幾らか意地悪そうに笑って見せた。