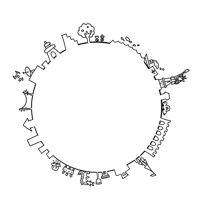

星屑をばらばらと散りばめたような店内で、その時、彼は確かに周囲と一線を画しているように見えた。正面に座る女の子たちを笑わせようと、身振り手振りを交えて面白おかしくエピソードを語る男の子の隣で、彼はただじっとそこにいることに徹しているようだった。それでも時々話を振られれば会話に加わる程度の社交性はあるようで、薄く笑みを浮かべるときに細められる目もとを、私はミントビアの入ったグラスを傾けながら、そっと盗み見ていた。
一度も染めたことがなさそうな、男の子にしては艶々しすぎている黒髪は、私の隣の席の女の子からは不評のようだったが(トイレで会ったときに「なんか野暮ったくない?」と言われて相槌に困った)、私にとっては彼の隣の席の男の子の傷んで金色に近くなっている茶髪の毛先よりは、清潔感があって好ましいものに感じられた。
なんとなく彼の瞳を見ていて頼んでしまったミントビアは、爽やかな香りの割には意外と大人の味がして、半分程飲んだところで舌先に残る苦みに辟易してしまっていた。私はそっとグラスをテーブルの脇に押しやってから、いつもより少しだけ高い女の子たちの笑い声の洪水に紛れようとする。横目でちらりと見た彼は、ちょうどトイレかなにかで席を立ったところだった。
「お、次何飲む?」
彼の隣の席の男の子と目が合った。人懐こそうな笑みを浮かべながら薄っぺらいドリンクメニューが差し出される。ここは笑った方がいいのだろうな、と彼の名前を思い出す前に、私も同じように笑みを作ってから、目に飛び込んできたメニューを指差した。モヒートね、了解。元気よくそう言って、男の子は呼び出しボタンを押した。
「はい」
彼が戻ってきた。周囲に気づかれないように自分の体で影を作りながら、私の目の前にそっと水を差し出し、それからミントビアのグラスを自分の方へ引き寄せた。隣の男の子の目線は既に場の中央に移っていたから、彼の気遣いはそれほど必要ではなかったのだけれど。
「あの…?」
「好きそうじゃなかったから」
ミントビアよりも幾分か濃い緑色の瞳が、濡れたグラスを指した。最後の力を振り絞るように炭酸の泡が底からこぽこぽと弱々しく浮いてきては弾ける。ありがとう、と言って、彼のくれた水のグラスに口をつけようとしたら、間の悪いことに店員さんの元気のよい声とともに、さっき頼んだモヒートが運ばれてきてしまった。「モヒートのお客様〜!」と言われ、おずおずと手を挙げると、その日初めて彼が盛大に破顔するのが見えた。
「飲めないのかと思ったんだわ」
「意外とおいしくなくて、これ」
水で口を濡らした後、モヒートのグラスを手にとった。彼は下を向いてひとしきり肩を震わせてから、ごくりと喉を鳴らした。きっと笑いを飲み込んだのだろう。
空いた皿を下げるために作業していた店員さんを呼び止めて、ミントビアのグラスも下げてもらう。店員さんのお盆の上で、ちゃぷんと寂しそうに緑の波が跳ねた。それはモヒートよりはやはり彼の瞳の色に似ていると思う。
「えっと…ブルくんは結構飲めるの?」
「よく名前覚えてたな」
「何ですかそれは。さてはブルくん、私の名前覚えてないんでしょう?」
「覚えてるよ。、だろ?記憶力には自信あるんだわ」
彼の答えに少しだけ違和感があった。答えに、というよりは答え方に、だろうか。その後も、私たちは隣の喧騒からかけ離れたたわいもない会話を続けたが、私は頭の片隅をずっとその違和感の正体を探ることに費やしていた。
ブルくんは時折り下がってくる眼鏡を中指と薬指でくいっと上げた。サイズが少し大きいのかもしれない。黒縁の少し角ばったデザインのその眼鏡は、確かに彼に似合ってはいたが、先程の彼の答え方同様、私にかすかな違和感を与えていた。
「こういう飲み会、あんまり参加しないの?」
違和感の答えは存外すぐに見つかった。私がそう聞いたとき、彼がぎょっとしたような顔でこちらを見た。私はその時になって初めて、彼のまあるい綺麗なグリーンを正面に捉えられたのだと気付いた。少し汚れたレンズ越しではあったが。
あ、と思ったときにはすぐに逸らされてしまい、急な動きに眼鏡だけ取り残されたみたいで、またずれてしまったそれを指で直す彼の仕草をそのまま目で追った。
「はどうなんだよ」
「私はたまにかなぁ。別に飲み会は嫌いじゃないし、彼氏もほしいんだけどね。なんだろう、こう、恋するというよりは、純粋に楽しいだけになっちゃって」
それは半分本当で半分嘘だった。いつもこういう飲み会で恋する気分にはなれない。友達からは、理想が高すぎるとか、夢みがちとか随分な反応をもらうが、仕様がないのだ。お互いをよく見せようと必死な空気のなかで、居心地の良い関係を築ける相手を見つけるのは至難の業だと思う。私はいつも、楽しむというよりは、気疲れしてしまっていた。嫌われないように合わせることと、好かれたいと思って行動することは、似ているようで全く別物である。
「で。ブルくんは?」
「俺は今日急に誘われて。本当は断るつもりだったんだけど…飯おごりだって言われたから」
「ごはんに釣られたの?」
「悪いかよ。今月ピンチだったんだわ」
ばつが悪そうにブルくんが残っていたビールを煽るので、私は呼び出しボタンを引き寄せた。ビールでいい?と聞くと、酔いのせいか羞恥のせいか分からないくらいほんのりと頬を赤く染めたブルくんが、ふてくされたように頷いた。それで私は、なんだかもう少しだけ彼と話をしていたいと思ったのだ。
二次会はカラオケだと言われて、ブルくんがあからさまに眉をひそめたのが分かった。真ん中から分けた前髪のせいで、彼の表情はとても読みやすい。お店を探す道すがら、きゃあきゃあと騒ぎ立てる一団から少しずつ距離を置きながら、二人並んで歩いた。
夜の繁華街はきらめくネオンとアルコールのにおいに満ちていた。千鳥足のおじさんやひんやりした風の吹くなか妙に薄着のお姉さん。私たちのようなお酒を覚えたばかりのあざとい若者たち。光と人でごった返すなかを歩いていると、ふわふわして宙に浮いた気分になる。カラオケには行く気はなかったが、このまま帰る気にもなれなかった。
「行かねーの?」
彼らの姿はもう見えなくなっていたのに、ブルくんが念のため、といった風情で聞くのがおかしかった。相変わらず目は合わせてくれなかったが、こちらを伺うような表情をしていることだけは見てとれた。
「私はいいかな。ブルくんは?」
「俺も行かない」
「カラオケ、嫌そうだったもんねえ」
「うるせーわ」
ブルくんが私の肩を軽く小突く。わざとらしく痛がるフリをしたが、彼には鼻で笑われてしまった。斜め上の横顔が憎らしい表情を作るが、それは全然嫌な感じではなかった。気安い穏やかでリラックスした雰囲気が、なんだか好きだなと思った。
相性はフィーリング。さっきまで一緒にいた友人が以前に教えてくれた言葉を思い出した。こういう飲み会で恋をするのが難しいと言ったときだった。一緒にいて居心地がいいかは、出会ってすぐにだって分かるのだと。そのときは半信半疑だったが、今なら分かる気がする。
「ブルくんは、もう、帰る?」
意識してしまうと、急に言葉がうまく紡げなくなった。片言のようになってしまった問いかけに、ブルくんは先ほどと同じように破顔してから、は?と聞く。こういうとき聞き返すのはとてもずるいと思う。そう思ったが、そのとき私は意外なほど素直になれていた。しばらく恋をしていなかったことで、変になっていたのかもしれない。なにしろ恋と変はとてもよく似ている。
「私はもう少し一緒にいたい、んですけど」
わたしがそう言って立ち止まると、ブルくんも歩くのをやめた。けれどすぐに後ろから人の波が押し寄せて、彼が慌てて私の手を引いた。ふわりと柔軟剤のような清潔なかおりが鼻をくすぐり、彼の肩口にいますぐにでも顔を埋めてしまいたいような気持ちになる。ああ、私変だ。きっと変になってしまっている。
ブルくんが私の手を引いて歩き出す。それは駅とは逆方向で、私の心臓はもうすぐ押しつぶされてしまう気がする。